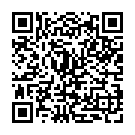今日も朝ごはん前の散歩。普段歩きなれないので、結構クタクタに。朝食にヨーグルトと黒砂糖をたっぷりかけたりんご、バナナ、イチゴを食べてチャージ。いろいろと思うように進んだが、急に山の上のコンサートに行くことにきめた途端、焦りが音にでる。自分の耳にもよくないので、明日はベートーヴェンの日に決めてコンサートへ。お目当はベートーヴェンのチェロソナタ作品69。そう、東京での5/13の曲目だ。他の曲はとてもいいけど、ベートーヴェンだけ違和感があった。自分の耳が、フォルテピアノでの演奏に慣れているだけかもしれない。けれどかかれていないルバートが頻繁にあって、相手と合わせるためのルバートや息継ぎが、はたしてベートーヴェンの目指したスピリットかどうか、それが気になって、8/8の東京コンサートに迎えるトラヴェルソのANAさんと長電話。バルト・クイケンの最近の著書に話題が及び、同じ方向性をもった演奏家と意見を交換できる喜びが湧き上がる。松尾芭蕉の引用がクイケン氏の本にはあるのだが、これが言い得て妙。つまり先人たちが歩いたところにただ行くのではなく、先人たちがなにを探し求めていたかを探し出す旅だと。フォルテピアノだとベートーヴェンの想像していたであろう音は比較的見つけやすいのかもしれないーでも音源も残されていないなか、やはり一番の手がかりは楽譜がすべてだと思う。その精神世界への旅人になり、楽譜を丁寧に謙虚に見ることが、少しでもベートーヴェンのそばで、その呼吸を感じ、マスターピースを享受できる幸せを噛みしめることになるんじゃないかと。モダンとか古楽とかじゃなくって、もっとその奥にある音楽への気持ちを今一度強く感じた日となった。
April 2015Archives
昨日の雨が、爽やかなグリーンの薫りをもたらした。練習前にも散策。夕食後にも散策。 自然にピアノが弾きたければ、自然から学ぶしかない。そんな声がどこからか聞こえた。自分に攻め込むのではなく、温かく、⇦これが結構難しい、やさしく、今自分ができることを謙虚にやる。ただそれだけのこと。でも朝練では今までイマイチだったところが、スッと通った。毎日違う見方、違う練習を考え抜くことが一番難しく、練習そのものがARTでなければならない。それにプラスして、納得できるまでの一回も無駄でない意識的な反復練習も必要。今日はご褒美で手打ちうどんと、夕方もお蕎麦で、練習の疲れも即効で癒えた。日本食恋しい。
今日は朝から来週日本へ戻る飛行機を決めて、そしたら急にこの小さな街をより知りたくて、歩いてみたくなった。外はポツポツ雨だったけど、気にせず歩いて20分。リーエンドルフという街にでる。いつもトラムから見ているはずの景色も、歩けば驚くほどの発見がある。小さな郵便局の跡がヨガ教室になってたり、小さな街でもツーリストインフォメーションがあり、ひたすらコンサート情報を集める。お目当ては先日もお世話になった、雑貨屋。ドイツ語の練習をしたくて入ったお店だったけどそこは生活支援センターで、なかでも中南米の女性がつくるハガキが魅力的^_^小一時間ほどみて、お店のお姉さんとお話しして外にでるとすごい雨。ササッとトラムに乗り込み自宅へ。珍しく長く歩く気、満々だったのに!
練習に戻って、今日はまずは東京での5/13のプログラムを復習。今日の新たな発見はなんだろう、早いパッセージを弾く時に次から次へと力を上手に手や指の中で橋渡しをしてくような感覚かな。力ずくでなく、謙虚に、でも流れのなかで。それから5/29のフィンランドでのプログラム。堀江さんのソロ二曲とベートーヴェンのソナタ作品54とバガテル作品33。ショパンのエチュード二曲と、プレリュードの四曲。今日はやっと「雨だれ」の気分で、弾いてみたけど、またここから再出発という様子。有名な曲だけに、より当たり前じゃない、新しい発見が必要!また明日再チャレンジ!それから香港でのプログラム。モーツアルト、シューマン、シューベルトの連弾曲。やっとモーツアルトの音が滑らかかつ生き生きしたものに少し近づいた。後期の作品だけあって、やはりシンプルななかに、全てが凝縮されていて、一筋縄ではいかない。
引き続きバーゼルよりお届けいたします^_^今日もまた練習のあとお散歩へ。雨の気配がすでにしていて土からなんとも言えない土っぽいかおりが漂います。そして桜の木の下に立つと、ポツポツとやってきた雨が桜の花びらをヒラヒラと舞うように落としてくれるじゃありませんか!一瞬ここがどこかわからなくなるような幻想的な桃源郷の世界は、懐かしい記憶を思い起こさせてくれました。
昨日の続きですが、あの日、ブリュッヘン最後の演奏会のあと、オーケストラのホルン奏者ハイスさん、ヒルケさん、そしてオーボエ奏者のアレーンさんと居酒屋へいきました。コンサート会場をあとにすると大粒の雨です。傘は一本しかなくみんなで濡れながら歩きました。その時の錦糸町に舞う雨の、普段だったらいやだなーと思うだけの雨が、あの日だけは、あの音楽の後、そしてかけがいのない友人と歩いたあの感覚が、雨の日の、肌にしっとり吸い付くような質感によって今も鮮明に思い出されるのです。
ピアノを弾くときも、毎日指先がふわっと優しく、時に激しく鍵盤をなぞると、毎日違った感覚がでてきます。昨日やったことの復習ではなくて、毎日が新しい感覚であること、そのために私の身体ができるだけ先入観なしのまっさらな空であること、そうであることがいかに重要でいかに難しいか。。日々の課題であり人生の課題であります^_^
今日の練習日記^_^
堀江さんの曲、「日記のような小曲集」が、やっと、自分の血となり肉となってくれるように、寄り添ってくれるようになってきた。やれやれ一安心。しかし最大の山場は「ページ10」である。終曲につながる、大事な局面。それをト長調とニ長調という一見心明るい調性で描かれているが、とんでもない!これは過ぎし日の美しい思い出、そしてそれはもう遡ることのできない、人生で一度しか現われない瞬間だと悟る。でもそう悟るのは、物語が終わったあと。そのワルツにいるときには、ただただ胸が締め付けられるー
私にとってはあの日、確か2013年だったか、ブリュッヘン指揮の18世紀オーケストラ日本最終公演で、皆が息を詰めて、一音一音噛み締めた、アンコールの、あのシュトラウスのワルツ。ただただ涙が溢れる、優雅で気品があって、でも二度と会えない音。お客さん、最後だけど、悲しまないでね、というメッセージを湛えてただただ音の波間に音楽の素晴らしさ、尊さを運んできた調べ。あの経験が、やっと少しずつ音になってきた。
http://www.h2.dion.ne.jp/~comodo/sub-tanno-5-13.html
ぜひご覧ください ⇧
昨日に引き続き、5/13のコンサートのことです^_^
初めて堀江さんの「日記のような小曲集」を弾いた時、ベートーヴェンのバガテルをすぐ連想しました。特に作品126の第3曲と、堀江さんの「ページ4」は、まったく違う音使いでありながら、深いところですごくつながっているような気がして、堀江さんの曲にじっくり向き合っていたら、ベートーヴェンの呼吸がなんだかとても恋しくなったのです。それで、記念すべき東京ピアノラボの第1章として、この二人の作曲家のまるごとをじっくり味わってみようと決めました。
堀江さんとは、私が野口体操に通い出した2012年ころに出会いました。体操を通じてのコミュニケーションはとても面白く、堀江さんの動き「そのもの」が音になってる!とおもった瞬間がありました。その気づきのあとは、堀江さんの話し方、歩き方、など、まるごとの堀江さんを観察!?して、堀江さんの楽曲と丁寧に向き合うと、毎日宝箱を開けるような、音楽の本当の愉しさに自ずと導かれていくような感覚でした。
このコンサートでは二人の作曲家の対比という表面的なことではなくて、「作曲家」という一人の人間が真摯に向き合ってきた音符、そして脈々と受け継がれてきた躍動感溢れる瑞々しい魂が「煌めく音符」となっていく過程をお客様と演奏者がサロンという親密な空気の中で味わうことできたら!
人生の中で忘れがたい瞬間に立ち会える喜びを皆さまとシェアしたいと心より願っております!
スイスより 4/14
5/13松濤でのコンサートについて
東京ピアノラボを立ち上げてはや一年!そしてひょんなことからスイスでの暮らしも始まり、山々に囲まれながらのピアノ練習は、毎日合宿のような気分になります^_^
以下が日本でのコンサートです。また足をお運び頂ければ嬉しいです^_^
国内外の優れた演奏家が集い、作曲家の魂を伝える音符たちの息遣いを、心をこめて読み解きます。忘れ去られたクラシック音楽の神髄を、今一度「サロン」という親密な空間で語りあう時、日本の音楽界に新たな扉が開かれます。
国際的に活躍中のミヒャエル・ツァルカはローマ、ベイルート、ボン、パリ、ジェノア、カラブリア、サルディーニャ、テルアビブ、シカゴ、ミネアポリス、ベルリン、メキシコシティー、クオピオ、フィラデルフィアにて数々の受賞歴を誇る。テンプル大学にて博士号取得後、2014年までストックホルムのリラ音楽院教授として活躍した。バロック音楽から現代音楽まで幅広く手がけ、モダンピアノ、チェンバロ、フォルテピアノ、クラヴィコード、スクエア・ピアノ、室内オルガンを専門とする。またボストン古楽音楽祭、北京紫禁城ホール、サンクトペテルブルグのエルミタージュ美術館、ニューヨークのメトロポリタン美術館でのリサイタルは好評を博す。クラヴィコードにてバッハ「ゴールドベルグ変奏曲」を演奏するなど独創的ななCD制作を続けており、ナクソスやパラディーノ・レーベルCDも国際的に高い評価を得ている。また後進の指導にも熱心で、世界中の音楽学校にて50回以上のマスタークラスを歴任。また彼の4つの学術論文もイタリアの「クラヴィコルディオ」やアメリカの「古楽ジャーナル」に掲載されている。